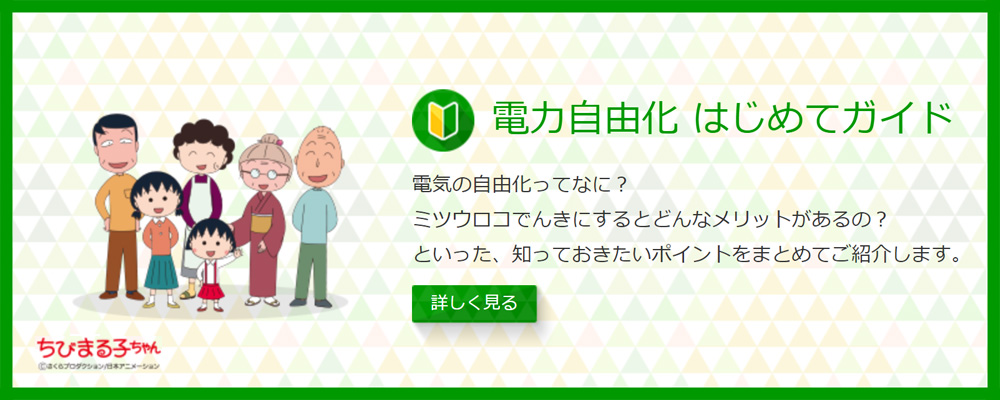太陽光発電システム
限りある資源に頼らず、無限に降り注ぐ太陽の力をあなたの生活に取り入れませんか? 太陽光発電システムなら、電気代の節約はもちろん、環境にもやさしいクリーンなエネルギーを活用できます。 毎日の暮らしに安心と持続可能な未来を。今こそ、太陽の恵みをあなたのエネルギーに変える時です。
蓄電システム
昼間に発電した電気を蓄えて、必要なときに無駄なく活用。災害時や停電のときも、蓄電システムがあれば安心です。電気代の節約にもなり、環境にもやさしいエネルギーの使い方を実現。 毎日の暮らしをもっとスマートに、もっと快適に。未来を見据えたエネルギーライフを始めませんか?
電力自由化
電力自由化で、電気も自分に合ったプランを選べる時代に。環境に優しい再生可能エネルギーを選ぶことで、地球にやさしく、お財布にもやさしい暮らしが実現します。電気代を節約しながら、サステナブルな未来に貢献しませんか? あなたにぴったりの電気プランを見つけて、もっとお得でエコな暮らしを始めましょう。
出光興産は徳島県小松島市に、国内初となる出力2000キロワット規模の次世代営農型太陽光発電所を建設する。農業と再生可能エネルギーを両立する発電所を実証する狙いで、2026年2月の完成を予定している。千葉県木更津市の同45キロワット設備(写真)で行った実証では、コメの収量に問題がなく、年間の発電量は日当たりのよい広い土地での太陽光発電並みを確保できることを確認している。 同社の次世代営農型太陽光発電設備は、太陽の動きに合わせて、農地の上に設置した太陽光パネルの向きを自動で調整する。耕作期間は農作物への日射量を最大化し、休耕期間はパネルへの日射量を最大化する。両面受光型のパネルを使い、裏側でも発電できる。パネルを支える架台の背は高く、農機の稼働を邪魔しない設計としている。 政府が40年度に再生可能エネルギーを主力電源化する方針を示した中、太陽光発電は再生エネの主力に位置付けられる。設置面積を現状の2、3倍にする必要があるが、大規模な太陽光設備を設置できる適地は減少している。そこで出光は農地に着目し、営農型太陽光発電の普及を目指している。
業界初のスマート農業技術開発 農林水産省から認定を取得株式会社ほくつう~能登半島復興を支える新しい技術開発への挑戦~ 株式会社ほくつう(代表取締役社長:早川信之、所在地:石川県金沢市)は、農林水産省に対して開発供給実施計画書を提出していましたが2025年2月27日に認定を取得しました。開発供給実施計画(以下「計画」という。)は、スマート農業技術活用促進法に基づき農林水産大臣が策定する基本方針に位置づけた開発供給事業の促進の目標の達成に資するスマート農業技術等について、民間企業等が開発・供給する取組の計画です。今回認定された計画は、当社既存の水田センサー(水位・水位水温)への取付も可能な業界初となる(当社調べ)無線化ユニットの開発です。農業(稲作)分野においては農業従事者数の減少等に伴い、一人当たりの経営耕地面積が拡大傾向にある中、水管理の省力化に資する水管理システムは、ほ場の大規模化が進むほど現場からの引き合いが強い状況です。また、特に、中山間地域においては複数のほ場が点在しているため、水管理システムを活用することで大幅な省力化にも資する一方、通信環境が整っていない地域が多く、水管理システムと水位センサーがクラウドを介して無線で繋がっているタイプの市販機器は活用が見込めない状況もあります。 他方、有線で接続しているタイプの機器も本システム含め市販されていますが、水田への設置については電線の長さに制限を受けるため設置場所が限定されてしまいます。ほ場の大規模化が進むほど、ほ場内の任意の地点での水位を計測した上で適切な水管理を行うニーズが高く、設置場所の適用範囲の拡大が望まれているところです。加えて小動物などに電線をかじられたり、草刈り作業などで誤って切ってしまったりとトラブルの原因にもなっています。このため、設置場所の広範囲化とトラブル率の低下に加え、既存センサー(水位・水位水温)への取付も可能な無線化ユニットの開発を進めることとしました。一方、弊社自動給水機の独自機能にスタンドアローン機能とホップ機能があります。スタンドアローン機能は、通信環境のないほ場でも、一度設定した計画通りにタイマー式で動作する機能であり、ホップ機能は、自動給水機が他自動給水機と通信し、通信エリアの拡張を平易に実現できる機能であります。この2つの機能と水位センサーの無線化を組み合わせることで、
積水化学工業株式会社(代表取締役社長:加藤敬太、以下「積水化学」)、四電エンジニアリング株式会社(取締役社長:黒川肇一、以下「四電エンジ」)および頴娃風力発電株式会社(取締役社長:松木敦則、以下「頴娃風力」)の3社は、フィルム型ペロブスカイト太陽電池を風車タワーの側面に設置するための共同実証実験(以下、「本実証」)を頴娃風力発電所(鹿児島県南九州市)にて2025年2月24日から開始しました。 1.本実証の背景 2050年の脱炭素社会実現に向けて再生可能エネルギー(以下「再エネ」)の導入拡大が求められており太陽光発電はその主力電源とされていますが、日本は平地面積が少なく従来のシリコン系太陽電池では適地が限られることが課題として挙げられます。一方、フィルム型ペロブスカイト太陽電池には、軽量で柔軟という特長があり、従来設置が難しかった場所に適用できる可能性が増すことから、再エネ導入量を拡大できる有力な選択肢として期待されています。 2.本実証内容 本実証は、積水化学が製造するフィルム型ペロブスカイト太陽電池を、四電エンジの設置・施工技術を用いて、頴娃風力(四電エンジの100%子会社)が運営する発電所の風車タワー側面へ設置。施工性および火山灰や塵の表面付着による表面防汚機能の評価などを検証していきます。 3.今後の展開 本実証で得られた結果を、ペロブスカイト太陽電池の防汚機能の改善やテーパー状の垂直曲面設備への設置方法確立へ活かしていくことで、ペロブスカイト太陽電池の適用拡大による脱炭素社会実現への貢献を目指してまいります。 (参考)■フィルム型ペロブスカイト太陽電池に関する積水化学のこれまでのリリースhttps://www.sekisui.co.jp/news/PSC/■四電エンジニアリング株式会社https://www.yon-e.co.jp/■頴娃風力発電株式会社https://www.yon-e.co.jp/company/information/affiliated/#company02
ジャカルタ – テスラは再び深刻な問題に直面しています。この電気自動車会社は、パワーステアリングアシスト機能の潜在的な故障により、米国(US)で376,000台の車両をリコールすると発表しました。この問題は、特に低速で車両を制御することを困難にし、事故のリスクを高める可能性があります。 リコールには、2023年のモデル3セダンモデルとクロスオーバーモデルYが含まれます。 米国高速道路交通安全局(NHTSA)に提出されたテスラの声明によると、この問題は、印刷された回路ボードの駆動モーターコンポーネントのオーバーボルテージブレイクダウンの可能性によって引き起こされます。 このリコールの発表は、テスラ株の価値に大きな影響を与えます。2月22日のロイター通信の発表によると、同社の株価は正午取引で3%下落した。全体として、テスラの株価は2024年に大幅に上昇した後、今年約10%下落しました。 「車両が動いているときにこの過剰な電圧状態が発生した場合、ステアリングは影響を受けず、視覚的な警告が表示されます。ただし、車両が停止すると、ステアリングホイールのサポートが失敗し、車両が再び移動するにつれて障害物のままになる可能性があります」とテスラは説明しました。 この問題は、ステアリング障害に苦しんでいるテスラの所有者からの多数の報告の後、NHTSAにとって懸念事項です。一部のオーナーはハンドルを回すことさえできず、他のオーナーは車両の制御に必要な労力が増加していると報告しました。NHTSAによると、この問題の結果、50台以上の車両が牽引されなければならなかったと伝えられている。 このリコールは、NHTSAによる1年以上の調査の後に行われます。2023年後半のロイターのレポートはまた、2016年以来、何万人ものテスラ所有者がサスペンションコンポーネントまたはステアリングコンポーネントの早期障害を経験していることを明らかにしました。テスラはこの問題に対処するために10月にソフトウェアアップデート(オーバーザエア)をリリースしましたが、公式リコールは今週発表されただけです。テスラは、1月23日の時点で、米国の影響を受ける車両の99%がアップデートをインストールしたと主張しています。 「テスラは、この状態に関連する可能性のある3,012の保証請求と570の現地報告を特定しまし